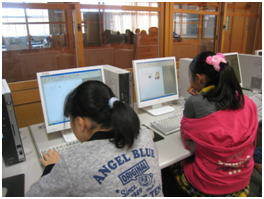5月13日 【種もみを水につける。】
種もみを5日間水につけて、水を吸わせ、発芽の準備をしました。
5月17日 【緑化】
☆児童の感想


5月20日 【緑化後の観察】
段ボールから種をまいたコップを取り出し、観察をしました。小さい芽が出ていました。
5月24日 【緑化後5日目】
苗がぐんと成長し、長いものは、約9cmありました。
☆ 児童の感想
段ボールを開けた時は、とても短く、小さくてかわいかったけど、今日は大きく成長していました。



6月17日 【代かき】
代かきと田植えの作業をしました。初めに、学習の流れを確認し、作業に取りかかりました。
重い土を3人で協力して運びました。
☆ 児童の感想
友達と協力して、バケツに土を入れました。バケツがとても重くなりました。




6月17日 【代かき】
土が入ったバケツに水を入れ、土が柔らかくなるまで混ぜて、平にしました。
☆ 児童の感想
全体の土が柔らかくなるまで混ぜるのは、とても大変でした。農家の方の苦労が分かりました。土の感触も気持ちよかったです。
6月17日 【田植え】
コップで育てた苗をバケツに植えました。5本の苗を倒れないようにしっかりと植えます。そして、水をバケツいっぱい入れます。☆ 児童の感想




7月 【水の管理】
|
7月15日〜19日 【中干し】 |
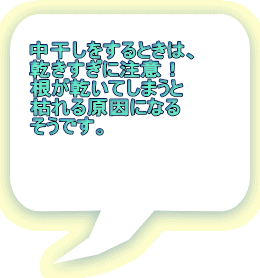


|
7・8月 【かかし作り】 |
|
大事な稲を鳥から守ろうとかかし作りをすることになりました。インターネットで、かかしの作り方を調べてきた児童がみんなに作り方を紹介し、材料を集めました。 『かかしの作り方』 1 骨組みを作る。 木材を十字に合わせて、釘とひもで固定する。 2 頭・顔を作る。 新聞紙や布で肉付けを行う。 3 体を作る。 新聞紙や布で肉付けをして、洋服を着せる。 4 ビニールを被せて保護する。 |




|
児童の感想 鳥から稲を守るために、かかしを作りました。みんなで協力して作ったので、楽しかったです。 |

花は、朝9時頃からほんの数時間しか咲かないので、見逃さないように観察することがポイントです。


夏休みに害虫が発生しました。害虫から稲を守るために、虫の嫌がる酢を薄めて、噴射しました。
児童の感想
夏休みの間に、稲が大きく生長していました。たくさん穂が出ていてこれが米になるのだなと思いました。

稲が立派に育ち、稲刈りをしました。かまの使い方を確認し、刈りました。その後、掛け干しをしました。
児童の感想
稲刈りをしました。まだ、小さかった稲があんなに生長してびっくりしました。生長した稲を刈るときに、わたしは緊張しながら「さびいしいな」と思っていました。だけど、あんなに生長したのでとてもうれしくなりました。米がたくさんとれるとうれしいです。
バケツが倒れるほどの大きさになっていました。太く、長く、たくましくなっていました。枯れたり、病気にかかったりしないで良かったと思いました。自分たちの育てた米を食べるのが楽しみです。





自分たちの手で脱穀をし、ボールを使ってもみすりをしました。そして、棒でついて精米しました。根気が必要な作業です。
児童の感想
もみすりでは、ボールでゆっくり上の方まですりあげました。なんとか、20粒位を玄米にすることができました。その後、棒でつきましたが、なかなか白米にはなりませんでした。昔の人の大変さがよく分かりました。
米が約1升収穫できました。家庭科の学習と関連させ、御飯を炊きました。子どもたちは、これまで大切に育ててきた米を調理するので、喜びや達成感にあふれた笑顔でした。
児童の感想
自分たちがつくった米を調理しました。ガラスの鍋に米を入れると、中の様子が見られるようになっていました。沸騰したとき、あわがいっぱい鍋の中から出てきました。そして、自分たちがつくった米をとうとう食べられるようになりました。頑張って作った米は、とてもおいしかったです。また、こんな体験ができたらいいなと思いました。
わたしたちは、これまで育ててきた米を食べることになりました。わたしは、とても楽しみでした。米を炊いたときに、もちのような香りがしておいしそうでした。御飯ができあがり、みんなで食べました。ふっくらしてもちもちでした。


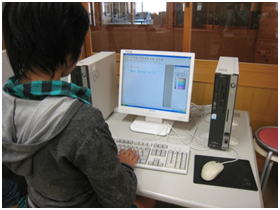
〜まとめ方を知ろう〜
稲作りで体験したことをまとめる学習を始めました。初めに、まとめ方を学びました。
1 テーマ
2 調べようと思った理由
3 調べる方法
4 調べて分かったこと
5 考察
次に、パソコンでまとめる方法を学びました。文字の大きさや色の選び方、絵・写真の挿入の仕方などを知り、実際に練習をしました。最初は、難しそうでしたが、友達と声を掛け合いながら、次々と技術を身に付けていました。
児童の感想
今日は、まとめ方の学習をしました。文字の打ち方は知っていましたが、写真の貼り付け方は知りませんでした。先生がしているのを見ている、難しそうだと思いました。しかし、やってみるととても簡単でした。ぼくは、パソコンを使って発表したいです。ぼくは、心の中で、「これで、パソコンマスターになったぞ。」と思っています。
発表の方を学習しました。昨年の5年生の発表の様子を見ると、楽しそうに発表していました。模造紙にまとめたり、ペープサートなどでまとめたりしていました。私は、紙芝居を選びました。どんな発表をしようか今後が楽しみです。