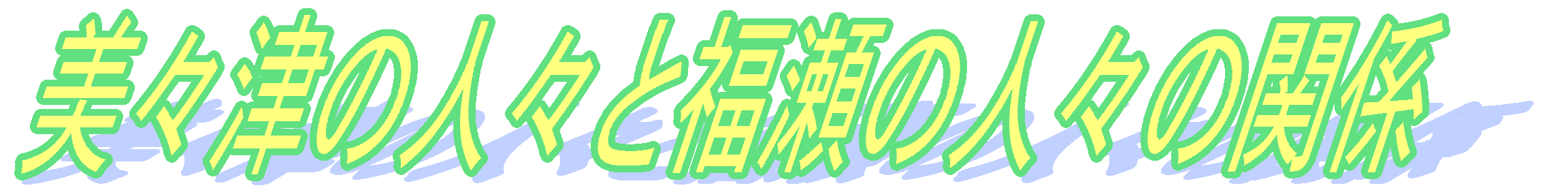
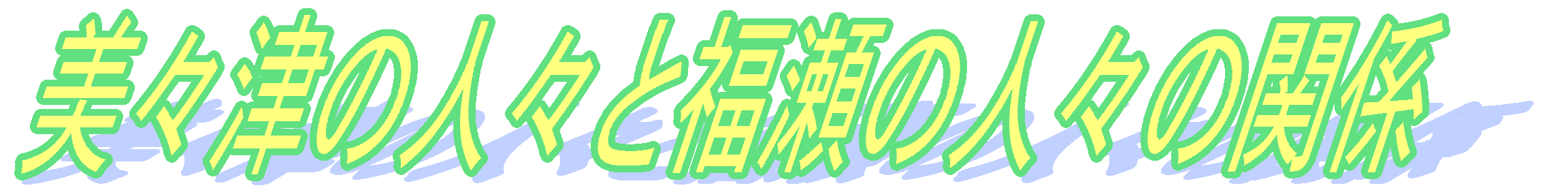
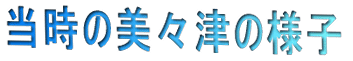
 |
| 【美々津の町並み】 (今でも、町並みが保存され、昔の面影を見ることができます。) |
| 美々津の町は昔はとても栄えていて、今でいう日向市ぐらい栄えていたそうです。「街にいく」というと、美々津をさしていたくらいでした。なぜ、そんなに栄えていたかというと、昔は、今のように道路も整備されておらず、船が運輸の中心でした。その中心となったのが美々津だったからのようです。 美々津には「船待ち」という職業の人々がおり、地元で取れた野菜などいろいろなものを大阪にもっていき売っていいました。また、大阪からたくさんのものが船で運ばれてくるため、ここでは珍しいものがたくさんあったそうです。美々津の女性は、大阪から入ってくる化粧品などを使っていたのでとてもきれいだと有名だったそうです。 |
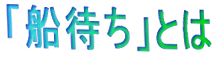
| 「船待ち」というのは、回船問屋のことだそうです。「船待ち」は船を入れる倉庫を持っていて、船が出るとそこに各地からの農産物などを保存していたそうです。そして船が帰ってくるのを待って、その農産物を船につみ、大阪に売りに行っていたので「船待ち」というそうです。 |
 |
| 「【美々津にあった倉庫】 しかし、これは、消防車の倉庫になっています。でもおそらく昔はこんな倉庫がたくさんあったのではないかと考えられます】 |
![]()
| 福瀬の農家の人々は、美々津の「船待ち」に炭を倉庫に預かってもらったり、船で大阪まで運んでもらったり、炭を検査してもらったりするのにお金がかかったそうです。そのために福瀬の人々は「船待ち」に多くのお金を払っていたそうです。お金がなくなったら、自分の山などを「船待ち」に預けて、お金を借りたりしていたので、そのお金を返したりするにもお金がかかった。それで、福瀬の人々の暮らしは、どんどん貧しくなっていった。 |
 |
| 【「船待ち」のあと】 【今では、日向市歴史民族資料館になっています。】 |

 |
| 【耳川の河口(美々津)】 (昔は、ここから、大阪に向けて、船が出発していたんだな〜〜。) |
| 僕は、開商の碑を見ると、「船待ち」はずるいなと思っていました。しかし、もし、この「船待ち」がいなかったら、福瀬の炭は、大阪に売ることはできなかったと考えると、「船待ち」がずるいということではないなと思い直しました。福瀬の人々は美々津の「船待ち」の人々を頼りにしていたし、「船待ち」も福瀬の炭を頼りにしていたのだと思いました。しかし、その流れでは、うまくいかず、もっと福瀬のためにいい方法はないかと考えたのが田辺清吉さんだったのだなあと思います。よく調べてみると、「福瀬商社」を立てた後、清吉さんは、今まで福瀬の人々が「船待ち」に預けていた山などを返してもらえるように話し合いをしたそうです。すると、「船待ち」は、返してくれたそうです。福瀬も豊かになり、お互いに分かり合えたのだなあと感じました。 |