
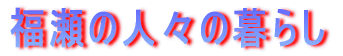

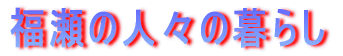
| ○ 当時は、ものが豊かでなく主食は米・麦・から芋(米だけのご飯が食べられるのは盆・正月ぐらい) 。 ○ おかずは漬物か干した魚。ごちそうが出たら今の何倍も喜びがあったそうです。 ○ 美々津(当時一番栄えていた港町)で福瀬で取れた野菜を魚と物々交換したりしていたそうです。 ○ 味噌や醤油など自分たちでできるものは自分たちで作っていた。 ○ 自分のことばかりでなく、他の人のことも考え、何かもらったら隣におすそ分けして、協力して生活していた。 |
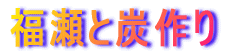
 |
| 【学校から見た福瀬の山】 (今は、ずいぶん杉木が植えてあります。) |
|
福瀬の山林の三分の一が福瀬区のもので三分の二が個人のものだったそうです。 |
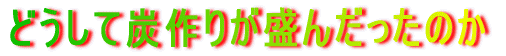
 |
| 【学校から見た福瀬の山2】 山が迫ってくるようです。 |
| 昔は,山の上は,焼畑にして畑になっていたり,戦争の跡が(西南戦争の跡)あったりしたので、木は山の上にはなかった。しかし、山の中腹や下のほうには、ナバ木(しいたけを育てる木になるもの)やクヌギの木などの雑木がたくさんあったそうです。それを使って炭を焼いていたそうです。 当時の農家の人は現金収入がほとんどなかったので、農閑期に炭を焼いて、それを売ることで、お金を得ていたそうです。 |
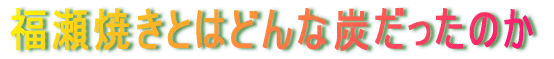
| 福瀬の炭(福瀬焼き)は,大阪でとても人気があったそうです。それは白炭(皮が残っていなく,水分がなく,たたくと金属のような音が鳴る炭。ご飯などに入れたりする)でなく,黒炭(皮が残っていて,よく火がつく)に近い、半白炭で、よく火がつき、品質がよかったからだそうです。 この炭がどうやってできたかは定かではありませんが、次のような話が残っています。 (炭を仕上げる段階で,奥さんが産気づいたので,煙の出る穴を全部閉めて帰った。その5日後炭を見てみると、たくさんの炭がとれてそれが黒炭に近い炭だった。) |
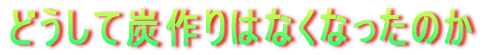
| 炭作りは,明治30年ぐらいにはしなくなったそうです。 その頃になると,植林などの仕事がはじまり,現金収入も出てき,生活が安定してきたので,炭作りを行わなくてもよくなってきたということでした。 |
 |
| 【学校から見える福瀬の山3】 確かに杉がたくさん植林されています。 |
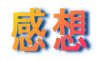
| 昔の生活は、貧しかったけど、地域の人たちみんなで協力し、仲良く生活していたと知り、すごいなあと思いました。 もし、自分たちがこの時代に生まれていたとしたら、自分のことばかり考え、もらったものも、人にあげたりなどしないと思います。貧しい生活だけど、心はやさしく温かかったんだなあと思いました。 そして、人々は、炭を作るのに、いろいろな雑木を使っていたようです。昔は、そんな木がたくさん福瀬にはあったんだなあと思いました。今は、人工林の杉が目立ちます。でも、僕たちは、緑の少年団などで、山桜やいろいろは広葉樹を近くの山に植えています。このような活動で、昔のような森林ができるといいなと思いました。 |