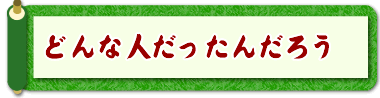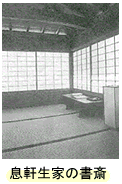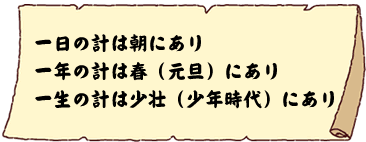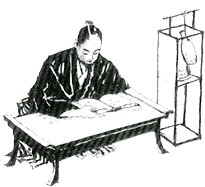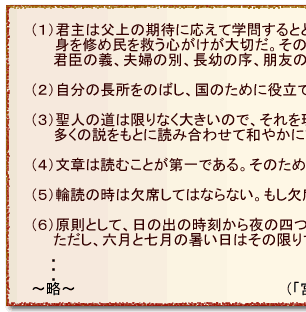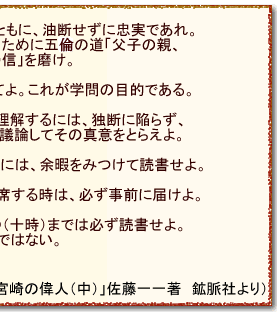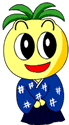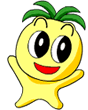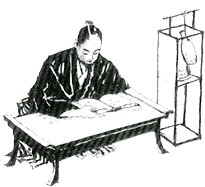 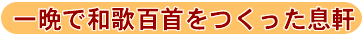
ある日の夕方、父の滄洲(そうしゅう)は仲平(ちゅうへい)に向かって、「仲平、和歌をつくってみよ。百首だぞ。」と言いつけました。
仲平は軽くうなずくと、夕食をさっさとすませて矢立て(やたて)を腰にさして、家を出ました。
その日は月夜でした。野道を北へ進むと、やがてだらだら坂です。そこから谷をわたって進むと、墓地(ぼち)がありました。松の木が黒くかげを落とし、草むらには虫の声が静かに聞こえていました。仲平は、ひとりで草むらに腰をおろすと、月明かりの中でさっそく和歌をつくり始めました。これから和歌を百首つくって、父に差し出そうというのです。
今までの勉強のおかげで、文字やことば、和歌のきまりなどもちゃんと知っていたので、和歌は順調にできていきました。それを一首一首ていねいに和紙に書いていき、やっと百首の和歌ができあがったときには、もう夜がしらじらと明け始めていきました。仲平は、疲れていましたが、よく百首つくれたという満足感もあって、大急ぎで家に帰りました。
父に見せると、父はそれをうなずきながら読み、その作品のできのよさに大いに満足しました。そして何よりも、この仲平の根性をたのもしく思うのでした。それは仲平が17歳、父の滄洲が49歳の秋のことでした。
※息軒は幼少のころ、仲平(ちゅうへい)と呼ばれていました。
(「郷土の偉人 安井息軒」 清武町教育委員会平成2年度版 より)
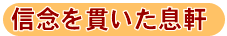
息軒が学んでいた江戸の学問所(昌平坂学問所)では、朱子学(儒学の一派)の考えだけが正しいとされていました。しかし、息軒は、自分が疑問に思うところがあれば、古い書物を調べ、その根拠を発見していく方法が真の勉強であると信じ、古学(儒学の一派)を学びました。しかし、他の塾生にはなかなか理解されず、仲間から嫌なことを言われたりしていました。
ある日、息軒は次のような和歌を作って、それとなく机の上に置いて席を立ちました。その句には、 |