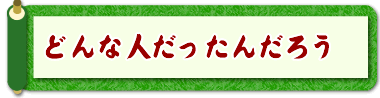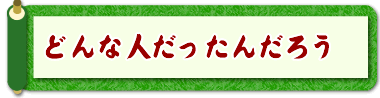| 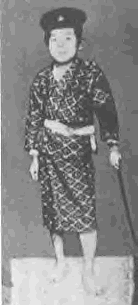 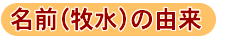
ものごころつく頃から、牧水は、雨に曇(くも)る坪谷の渓谷(けいこく)と尾鈴山が大変好きでした。短歌をつくりはじめた中学生のころは、雨山(うざん)とか白雨(はくう)とか自分を呼んでいましたが、19歳の時、牧水と名乗るようになりました。それは、当時、彼が最も愛していたものの名前二つをつなぎ合わせたものでした。「牧」は、母の名前「まき」を漢字に直し、「水」は渓谷や雨から付けられたのだそうです。

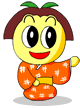 明治36年(1885)、中学校最終学年を迎えた牧水は、将来の進路を決めなければなりませんでした。
明治36年(1885)、中学校最終学年を迎えた牧水は、将来の進路を決めなければなりませんでした。
牧水の家は代々医者でした。医者の学校に進学して、父の後を継がなければならないのか、それとも自分の好きな文学を目指すべきかで悩みました。
文学のことに詳しい柳田先生が、牧水の優れた才能を認め、早稲田大学の文科に進むようにと勧めました。牧水は校長先生にも相談し、どうすべきか意見を聴(き)きました。校長先生も早稲田大学の文科を勧めましたので、父や義兄にも相談して早稲田大学の文科への進学を決意しました。
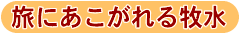
牧水は、自然を求めて旅にでて、多くの短歌を残しています。若い頃は、幼少年期からあこがれていた広大無辺の海を求めて旅をした牧水でしたが、後年は、ふるさとの原風景を求めるように、いろいろな山や渓谷を求めて旅をつづけました。
日本各地に多くの歌碑が建てられています。
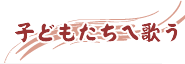
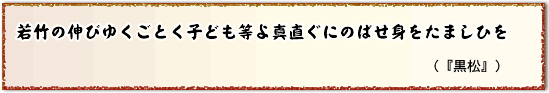
 |
|
| 若竹が伸びゆくように、子ども達よ、まっすぐにのばせ。身を、そして魂を。 |
 |
|
| 大正12年の秋ごろの作。「やよ少年たちよ」九首の冒頭の歌である。牧水は子ども達を心から愛した。わが子はもちろん、すべての子ども達を愛した。子どもの純粋の心を大切に思っていたからである。「若竹の伸びゆくごとく」の比喩がすがすがしい。子どもに対する牧水の願いと祈りが平明に表現されている一首である。
|
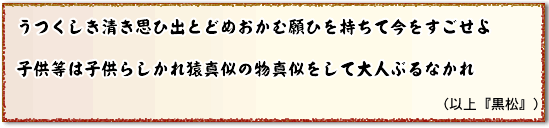 |
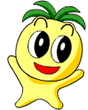 |
【歌の意味・歌の鑑賞】
(『命の砕片』 伊藤一彦著 鉱脈社 より) |
|