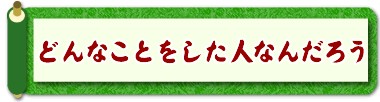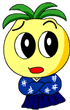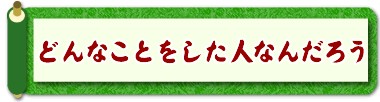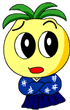|
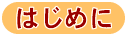
1950年代までは、多くの人たちの興味が火星に集中したため、木星観測をする人は少なかったのです。しかし、その後、木星観測に火がつき、1960年から1980年代まで大きな発展を遂(と)げます。
一方、薦田一吉は、昭和12年(1937)から始まった日中戦争から第二次世界大戦の頃まで、研究がやりにくくなっていく中にあって、イギリス天文学会の報告書を手に入れ、辞書を片手に夜空を仰ぎ、手製の望遠鏡、手作りの天文台を完成させ、独学で天体観測を行ったのです。
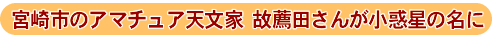
(『平成10年(1998)4月17日、宮崎日日新聞』より)
推薦者は、「すごい人だった。こういう方の名を残すことは日本の天文学界にとっても誇り」と感想を述べた。』
※実際に小惑星を発見したのは他の天文学者円館金さんら二人であった。
国際天文学連合(IAU)では、「発見者に名前を申請させる」規定になっている。

18年間にわたって得た628枚の木星のスケッチと331回の観測の結果を「1944〜1961年における木星面の主要なる諸現象について」という報告文にまとめ、「天界」(476〜478号昭和40年(1965))に発表しています。
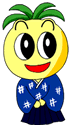
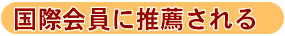
『1951年(昭和26)、36歳のときに、木星の自動周期に関する論文が認められ、アメリカの研究団体から日本人として5人目の国際会員に推薦され、学会や関係者の注目を浴びます。』
(平成10年(1998)12月23日 宮崎日日新聞』より)
|