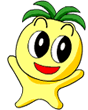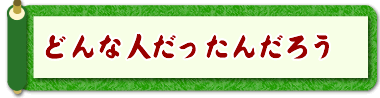
|
『手製の望遠鏡で天体観測に打ち込み、とりわけそれまで(1950年代)あまり注目されなかった木星の表面の変化に興味を抱き、克明なスケッチと調査書を日本やアメリカの学会に送り続ける。』(注1)
『手造りの天文台を裏庭に完成させた昭和元年(1925)ごろの観測仲間たちは「当時はたいへんな食糧難で暮らしも心も荒れて、乾ききった状態でしたが、彼が主催する観月会や、流星群観測会などに参加することによって、夢や潤いを与えてもらうことができました。とにかく星一筋の人でした。あまり強くない体のいったいどこに、あんなエネルギーがあるのだろうと、感心し合ったものです」と口々に語っている。』(注2) (注1〜2) (『平成10年(1998)12月23日、宮崎日日新聞』より)
宮崎は天体観測に適したところで、スターウォッチングも盛んです。木星観測の草分けであった一吉は、子どもたちのための星空教室を開くなど、普及にも努めました。 また、天体に興味のある学生たちが一吉をよく訪れ、星についての話に花をさかせたということです。
(『平成10年(1998)12月23日、宮崎日日新聞』より)
|
||||||||
|