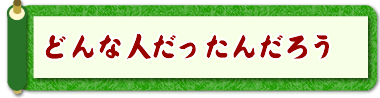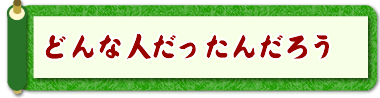| 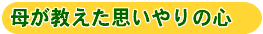
十次が生まれた村は、貧しい村で、十次の同じ年頃の友だちの多くが、日々の食べ物にも困るような暮らしをしていました。その中で、両親が亡くなり、だれも世話する者がいない少年がいました。十次の母は、その少年の親代わりとなって、十次と同じように愛情深く育てました。
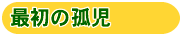 
明治20年(1887)、十次22歳のとき、医者としての実習をしていた診療所の隣に大師堂(たいしどう)がありましたが、そこは、巡礼(じゅんれい)の人や貧しい人たちの宿でもありました。十次は毎朝のように、大師堂に出かけていき、その人たちの話を聞いたり、食べ物をあげたりしていました。そんなある日、母子3人の巡礼と出会い、「子ども二人を連れていては、だれもやとってくれず食べていくことができない」という母親の話に同情した十次は、一人をあずかることにしました。
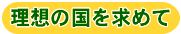
十次は、茶臼原に孤児院を移し、働くことを大事にし、自然を愛するという理想の国づくりをめざしました。

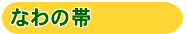
これは、十次が7歳のころのお話です。
| その年も、にぎやかに天神様の秋祭りがおこなわれていました。
この日ばかりは、大人も子どもも、晴れ着をきこんでお祭りに出かけました。
十次は、お母さんがいそがしい仕事の合い間につくってくれた、つむぎの帯をしめて、 神社までやってきました。
すると、大鳥居(おおとりい)あたりで、子どもたちが集まってさわいでいます。
近よってみると、友だちの松ちゃんが、目になみだをいっぱいためていました。
松ちゃんが、わらの帯をしめているのをはやしたてているのでした。
十次は、むらむらと怒(いか)りがこみあげてきました。十次は自分の帯をとると、 松ちゃんにわたして、代わりに松ちゃんの帯を自分の腰にまきつけました。
「これでいいんだな。」十次は顔を真っ赤にしながら、まわりを取り囲んでいた子どもたちをにらみつけました。子どもたちは、あまりの十次の気迫におされて、しいんとなってしまいました。
十次は、しっかりと松ちゃんの手をにぎると、祭りの音のする方へ歩いて行きました。
日もくれかける頃、家の近くまで帰ってきた十次は腰(こし)にしめているなわの帯を見て、はっとしました。遊びに夢中になって、帯を返してもらうことをすっかり忘れていたのでした。
十次は、どきどきしながら、やっとの思いで家の中にはいり、うなだれてお母さんの前に立ちました。そして、消えいりそうな声で、松ちゃんに帯をわたすことになったきょうのできごとを話しました。
すると、お母さんは、十次の手をやさしくつつみこんで、にっこりしながら、「それはよいことをしましたね。」とほめてくれたのでした。
この一言が十次の心にしみこんでいきました。 |
|