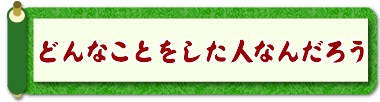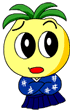|
 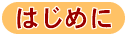
文明開花の時代にあって、明治13年(1880)、福島邦成は、宮崎県の将来を考え、私費を投じて橘橋を架けた人物です。
明治6年(1873)に初代宮崎県が設置されましたが、江戸や長崎に遊学して見聞を広めた邦成は、宮崎の近代化に大きく貢献しました。
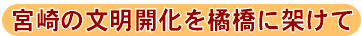
明治6年(1873)に大淀川架橋の話がもち上がりました。しかし、治水の行われていない大淀川は洪水を繰り返し、「大淀川架橋は不可能である」と橋の起工は中止されました。
邦成が「橘橋」を架ける前にも、いろいろな人による大淀川への架橋計画がありましたが、実際に架橋までには至りませんでした。
 橋が架かるまでは、人々は大淀川を船で渡っていました。台風や雨などの水量の多い日は宮崎の南北の交通は断たれていたのでした。
橋が架かるまでは、人々は大淀川を船で渡っていました。台風や雨などの水量の多い日は宮崎の南北の交通は断たれていたのでした。
邦成は、文明開化の時代に大淀川への架橋こそが、宮崎の発展につながると考え、私費をはたいて架橋をすることにしました。大淀川への架設の許可がなかなか下りなかったのですが、官庁に必要性をねばり強く訴え、やっと明治13年(1880)に許可がおりました。
 明治13年(1880)4月、邦成の架けた初代橘橋は4ヶ月後、洪水のため流失してしまいました。しかし、橘橋の必要性を強く感じている邦成は それにもめげず、その直後の10月に再び次の橋を架けました。 明治13年(1880)4月、邦成の架けた初代橘橋は4ヶ月後、洪水のため流失してしまいました。しかし、橘橋の必要性を強く感じている邦成は それにもめげず、その直後の10月に再び次の橋を架けました。
そして明治16年(1883)には、橘橋と橋板や木材を県に寄付しました。その木材などをもとに、2代目橘橋が県により架けられました。
架橋により、対岸への往来はもとより、医薬品を早く届けることができるようになったり、対岸の火事に火消し衆がすぐかけつけたりすることができるようになるなど、宮崎の人々の暮らしにたいへん役だったのです。

邦成が天然痘の牛痘を持ち帰った嘉永2年(1849)の延岡藩では、まだ漢方医学が主流であり、西洋医学の牛痘接種は行われていませんでした。
そこで邦成は地元の宮崎市に帰り、宮崎の人々に「天然痘に一度かかったら、もう二度となりません。人の痘瘡(とうそう)の変わりに牛痘を植えても同じことで、二度と天然痘にはかかりません。日本国中宮崎以外ではどこでもやっています。」と説明して回りました。
しかし、なかなか理解してもらうことができず、自分の息子(理一郎)らに牛痘接種を行い、宮崎の人に安心と信用を与え、その施術(せじゅつ)を広めていきました。

長崎医学の教育を受けた邦成は、新しい西洋医学を宮崎で普及することの必要性を痛感しました。
「今まで自分だけが西洋医学を学び、医師としてできる範囲で施術してきた。しかし、五十歳を越え、自分の命にも限度がある。一人の医師が診(み)ることのできる患者は限られている。教育者として宮崎に医師を育てることが自分の役目に他ならない。」と考え、宮崎の医師たちの勉強の場、宮崎の医療のレベルアップのために宮崎医院を設立しました。
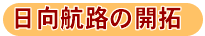
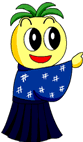 西南戦争以前の宮崎で、病院などの薬は大阪・神戸から運ばれてきていました。そのため、海運が物資の搬送(はんそう)に重要な役割を果たしていたのです。しかし、大阪・神戸と結ばれている美々津港や東海(とうみ)港と赤江港は航路が確立されておらず、邦成は医療に必要な薬品の入手に大変不便を感じていました。 西南戦争以前の宮崎で、病院などの薬は大阪・神戸から運ばれてきていました。そのため、海運が物資の搬送(はんそう)に重要な役割を果たしていたのです。しかし、大阪・神戸と結ばれている美々津港や東海(とうみ)港と赤江港は航路が確立されておらず、邦成は医療に必要な薬品の入手に大変不便を感じていました。
そこで、明治11年(1878)、120トンの蒸気船「日向丸」を購入しました。美々津、広瀬、赤江、内海の4港を結ぶ沿海航路を宮崎で初めて開いたのです。
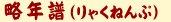
| 文政2年(1819) |
|
宮崎郡大田村(現宮崎市)に生まれる。 |
| 天保7年(1836) |
17歳 |
江戸に行き、儒学、蘭学、西洋医法内外科等
を学ぶ。 |
| 嘉永3年(1850) |
31歳 |
県立延岡中学校(現、延岡高校)を卒業す
る。 |
| 明治4年(1871) |
52歳 |
宮崎医院を設立する。 |
| 明治6年(1873) |
54歳 |
東京に遊学する。 |
| 明治12年(1879) |
60歳 |
蒸気船「日向丸」を購入し、日向航路を拓
く。 |
| 明治13年(1880) |
61歳 |
4月:大淀川に「橘橋」を架ける。 |
| |
|
8月:洪水のため「橘橋」が流失する。 |
| |
|
10月:再び架橋する。第二「橘橋」が完成す
る。 |
| 明治17年(1884) |
65歳 |
1月:「橘橋」を宮崎県に寄付する。 |
| |
|
6月:県により第三「橘橋」が架橋される。 |
| 明治31年(1898) |
79歳 |
79歳で亡くなる。(※没年齢については諸説
ある) |
|
|
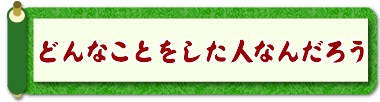
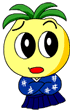

 橋が架かるまでは、人々は大淀川を船で渡っていました。台風や雨などの水量の多い日は宮崎の南北の交通は断たれていたのでした。
橋が架かるまでは、人々は大淀川を船で渡っていました。台風や雨などの水量の多い日は宮崎の南北の交通は断たれていたのでした。