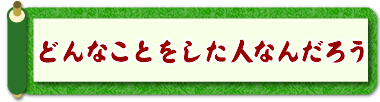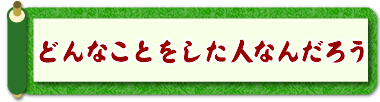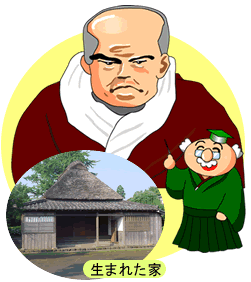
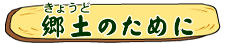
飫肥藩(おびはん)に「天然痘(てんねんとう)の予防のための種痘(しゅとう)」や「かいこを育て糸をつくること」「二期作」をすすめました。
「老人を敬うことは、人として大切な道です」と今から150年以上も前に「敬老のすすめ」を進言し、敬老の会を実現させました。 |
※二期作:同じ耕地に作物を年に二回栽培すること。主に稲作をいう。 |
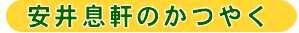
|
| 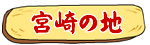
清武の「明教堂(めいきょうどう)」という学校で、ふるさとの子どもたちに学問を教えました。
明教堂では、年齢(ねんれい)には関係なく進級でき、儒学を中心に歴史と武術を教えました。
また、 飫肥(おび)藩に「振徳堂(しんとくどう」)という学校ができると、そこでも教育に専念しました。 |
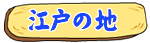
江戸に「三計塾(さんけいじゅく)」という塾を開き、2000人というたくさんの人を教えました。
息軒の教えを受けた人たちの中には、明治の新しい国づくりを支えた人が多くいました。
また、 63歳で、江戸幕府の学校であった「昌平坂学問所(しょうへいさかがくもんじょ)」の先生となりました。
|

 息軒は、「救急惑問」という本の中で、「日本の人々の生活や習慣は、世界の国々とくらべてすぐれています。しかし、お年寄りを大切にする心はおとっています。よい教えが、人々の間に広まっていないからです。このよくない点を改めるには、まずお年寄りを集めて、敬老の会を始めたらよいのです。」と書き、そのためのいろいろな方法を述べています。
息軒は、「救急惑問」という本の中で、「日本の人々の生活や習慣は、世界の国々とくらべてすぐれています。しかし、お年寄りを大切にする心はおとっています。よい教えが、人々の間に広まっていないからです。このよくない点を改めるには、まずお年寄りを集めて、敬老の会を始めたらよいのです。」と書き、そのためのいろいろな方法を述べています。
元治元年(1864)、息軒の念願がかなって、飫肥と清武で敬老の会が行われました。子どもや孫に付きそわれた老武士たちがお城に招かれ、殿様や家老のお話があった後、たくさんのごちそうをいただきました。そのころの食事は、一汁一菜といってとても質素なものでしたが、その日は、一汁三菜のほかに魚2品と酒がふるまわれました。老武士たちは、大変喜び、昔の話をしながら、楽しい一日を過ごしました。また、町人や農民にも、代官所などで同じようなことが行われました。
このように、「老人を敬うことは、人として大切な道です。」と150年前に息軒は殿様に進言し、敬老の会を実現させたのです。
(『郷土の偉人 安井息軒』清武町教育委員会平成2年版より) |