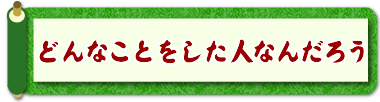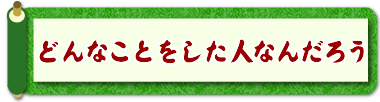児玉久右衛門は、元禄2年(1689)(江戸時代)西都市三宅(みやけ)に、当時のしょう屋の二男として生まれました。
久右衛門がつくった杉安いぜきと用水路ができる前、この地いきはあれ地が多くて田が少ない上、日でりの害などで作物がよくできませんでした。それに年ぐの取り立てもきびしく、人々はおもにあわやそばを食べてくらしていました。まずしい暮らしのために、村を出て行ってしまう人々もいました。
久右衛門はそのような村の人々の苦しいくらしを見かねて、村の人々のために、何かできることはないかということをいっしょうけんめい考えて、一ツ瀬(ひとつせ)川の水をどうにかして引こうと決心をしたのです。
|
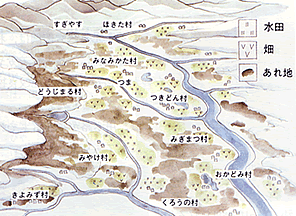 |

杉安用水路ができ、新しい水田がつくられ、米作りがさかんになると、人々のくらしもだんだんよくなっていったそうです。人々はよろこび、久右衛門に感謝(かんしゃ)したそうです。今でも、杉安用水路は水田に水を送り続けています。
| 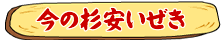

いぜきによってためられた一ツ瀬川の水が取り入れ口からいきおいよく用水路に流れていきます。
用水路は、およそ10km下流の黒生野(くろうの)までのびていて、全部の用水路を合わせると、およそ20kmもあります。 |
|
|