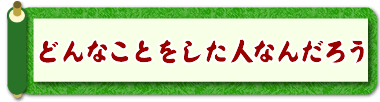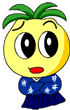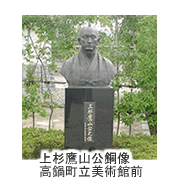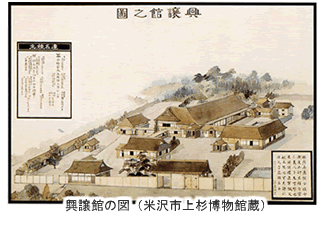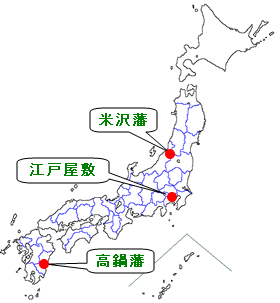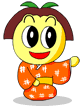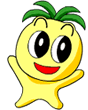|
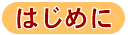
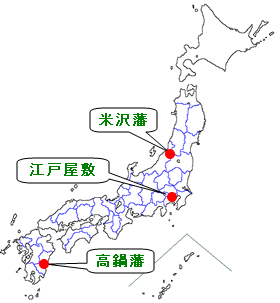
今から約250年前、鷹山は高鍋藩主秋月種美(たねみつ)の二男として江戸屋敷に生まれました。祖母豊姫が米沢藩出身という縁によって、10歳のとき米沢藩主の養子となりました。
17歳で第10代藩主となったとき、米沢藩はばく大な借金をかかえ、民衆も苦しんでいました。鷹山はこれらを乗り越えるために、自分から模範を示して節約に努め、新たな産業をおこし、財政の立て直しに全力で取り組みました。
35歳で引退後も政治に参加し、井ぜき建設などの大事業を完成させ、養蚕・織物・陶磁器・和紙などの産業を盛んにしました。
「なせば成る、なさねば成らぬ何事も、成らぬは人のなさぬなりけり」という言葉を残した名君でした。
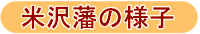
上杉家は関ケ原の合戦で石田三成に味方をしたため、徳川家康により会津(福島県)120万石から、米沢(山形県)30万石に減らされました。さらに3代藩主のころは、半分の15万石にまで減らされてしまいました。藩の収入はこれまでと変わらないのに、家臣の出費が多く、藩の財政は大変苦しくなりました。借金総額も大きな金額になっていました。
収入を増やそうとして重税を課したので、逃げる者も多く、13万人の人口は、1760年ごろは10万人程度にまで減少していました。
※石高・・・土地の値打ちを,生産される米の量で表すこと。
(石高)=(面積)×(米の反あたり収穫量)
 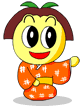
長い間上杉藩の領民の心と生活の中に根深く残っているぜいたくさと、それに伴う多大な支出を、上杉謙信時代の倹約を旨とした昔に返すことが大事であると考え、大倹約令を実行しました。そのために「志記」という倹約の趣旨を詳しく書いた文書を藩士にあたえました。「今日の生活を犠牲にしてでも、明日の立ち直りを考えなければならない。無駄な経費は今後10年間省略する。」といった極めて厳しい内容でした。
そして鷹山は、「それには、まず私が私の身の回りから実行するから、気づいたことがあったら遠慮なく言ってくれ」と自ら率先して実行していく熱意と意欲を示しました。
毎年おそってくる大洪水やかんばつによる田畑の流出や農民の逃散など悪条件が重なって、せっかく起こした耕地が荒れ果てて、農民が耕作への希望を失っていました。このことを心配していた鷹山は、「籍田の礼」を行いました。この儀式は、鷹山や家臣一同が神社に参拝したのち、ある村の荒れた田の土に対して、数回ずつ鍬(すき)入れするものでした。これによって、農業の大切さを領民に知らせ、農業を盛んにしたいと思う鷹山のねらいがありました。
藩主自らが鍬を取って耕すことは前例のないことで、農民はいたく感激し、田の開墾にこれまで以上に努力するようになりました。また武士たちも農業の大切さを心から悟り、荒れた田の開墾に進んで従事しました。
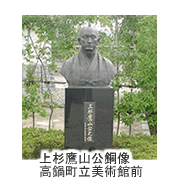
藩の経済を再建することを目標に、養蚕・製糸・織物・製塩・製陶などの産業の開発に取り組みました。まず、田畑を開墾させ、漆(うるし)・こうぞ・桑(くわ)などを栽培させました。漆の実から漆蝋を生産し、こうぞから和紙を作り、桑の葉で蚕(かいこ)を飼って、生糸をつむぎ絹織物を作りました。
特に養蚕については、「養蚕手引」の作成や、他藩の養蚕家による指導などによって、養蚕に対する領民の関心を高め、絹織物の生産を向上させました。技術はその後も引き継がれ、現在でも「米沢印」のある絹織物は最高の部類として高く評価されています。
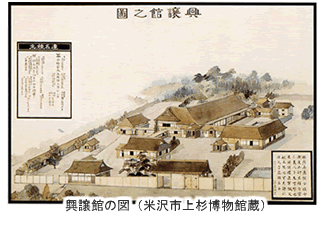
鷹山は、米沢藩のこれから100年間の計画を立てるには、優秀な人材育成が必要であると考え、そのための学問の場としての「興譲館」を創設しました。「興譲」とは、譲を興すことで謙遜(けんそん)の心をもって相手を尊重する道を修業させることです。この学問所では、古来の聖人君子の道徳を学び、高ぶらない謙譲(けんじょう)の美徳を身につけさせ、どんな地位についても恥じない人を作ることを目的とした教育が営まれました。
鷹山は子どもや老人を大切にする政治に着手しました。まず、子どもが生まれたけれど、おむつを準備できないなど貧しい家庭に対して支給する出生手当金や、15歳以下の子どもを5人以上もっている家庭に支給する養育手当金を制度化しました。
また、毎年1月、村や町の90歳以上の老人を城に招いて、敬老会を開きました。かつて老人を邪魔者扱いにし、あるいは無関心に過ごしてきた人も、以後は長寿の老人を出すことを家の誇りとするようになりました。
(以上「上杉鷹山公」(渡部図南夫著)参考)
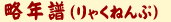
| 宝暦元年(1751) |
|
日向国(宮崎県)高鍋藩主、秋月種美(たねみつ)の二男、松五郎として江戸に生まれる。 |
| 宝暦1年0(1760) |
10歳 |
米沢藩主、上杉重定の養子となる。 |
| 明和2年(1767) |
17歳 |
第10代米沢藩主となる。「治憲」と改名する。武士に大倹約を命ずる。
|
| 安永元年(1772) |
22歳 |
「籍田の礼」をはじめる。 |
| 安永2年(1773) |
23歳 |
重臣7人が改革政治に反対して「七家騒動」を起こす。 |
| 安永5年(1776) |
26歳 |
興譲館を再興し、学制を制定する。 |
| 天明5年(1785) |
35歳 |
隠居。家督を治広にゆずった後も藩政を指導する。 |
| 享和元年(1802) |
52歳 |
「鷹山」と改名する。 |
| 文化3年(1806) |
56歳 |
「養蚕手引」を発行・配布する。 |
| 文政5年(1822) |
72歳 |
72年の生涯を閉じる。 |
|
|