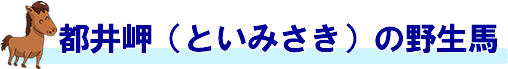

![]()
 ここには、丘に林に谷に群れ遊ぶ「御崎馬(みさきうま)」が生活しています。御崎馬は、長野県や北海道の馬などとともに日本在来馬といわれ、今から2000年も前の縄文時代から弥生時代中期にかけて中国大陸から導入された馬が起源とされています。
ここには、丘に林に谷に群れ遊ぶ「御崎馬(みさきうま)」が生活しています。御崎馬は、長野県や北海道の馬などとともに日本在来馬といわれ、今から2000年も前の縄文時代から弥生時代中期にかけて中国大陸から導入された馬が起源とされています。
今から約300年前、
御崎馬は、牧場開設当初から、自然のままで管理され、そのため御崎馬の習性や体形などは野生状態のままです。このため、「野生馬」といわれています。昭和28年「自然における日本特有の家畜」として、国の天然記念物に指定されました。このことで、これまで以上に人間が世話をすることはできなくなりました。
現在、都井岬では、88頭(令和4年1月27日現在)の御崎馬が生活しています。

![]()
野生状態で生活する馬はだいたい群れを作って生活します。これは1頭のオス馬に数頭のメス馬と子馬で構成されたものです。しかし、子馬は1〜2歳ぐらいまでには生まれた群を離れ、メスの子馬は別の群れに入るか、若いオス馬と新しい群れを作ります。
繁殖(はんしょく)シーズンの4月〜6月には、群れの若いオス馬とオス馬との争いが絶えません。
![]()
御崎馬(みさきうま)には2つの大きな特徴があります。
その1つは、日本古来の在来馬としての特徴です。御崎馬に見られる
2つめは、過去300年にわたる厳しい自然の生活から生まれた御崎馬特有の野性的な生態です。前に述べたような群れを作って繁殖し、季節ごとに最適の場所に移動していく習性は、飼育馬や動物園の馬では見られないことです。
|
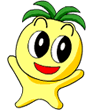 |
■つぎへ |
| ■幸島の野生ザル | |
| ■御池(みいけ)野鳥の森の鳥たち | |
| ■もっと詳しく知りたい人は | |
| ■前へ | |
| ■ホーム |