学校概要
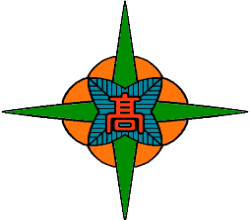
大地(農業と生活)に四本の杉(林業)と柑橘(園芸)を配し、中央に高校の高をおき図案化したもので、農業、園芸、林業、生活の四コースが大地にしっかりと根を張り、 豊かな、農業の姿を描きながら、生々発展する様子を象徴したものです。この校章は昭和42年に本校が南郷町に設置された時に図案化され、現在もこれを使用しています。
閉校に寄せて

早春の兆しがあちらこちらで見受けられるようになり、校庭の草木たちも凜として香しく新緑を芽吹かせ始めております。
このような佳き日に、本校をこれまで支えて頂きました多くのご来賓や同窓会、歴代PTA、旧職員の皆様方のご臨席を賜り、宮崎県立日南農林高等学校閉校式典を挙行できますことを衷心より感謝申し上げます。
宮崎県立日南農林高等学校は、日南市星倉にありました旧県立日南農林高等学校と南郷町栄松にありました県立南郷園芸高等学校が再編整備され昭和42年4月に現在の日南市南郷町中村に設置されました。
旧日南農林高等学校は、日清戦争後間もない明治30年3月に飫肥農業補修学校として飫肥町の「春日館」を仮校舎として開校されました。その後、昭和3年4月に宮崎県立飫肥農学校、昭和22年4月に宮崎県立吾田高等学校、昭和26年6月に宮崎県立日南農林高等学校と改称し、昭和44年3月に72年間の栄えある歴史に幕を閉じました。
また、昭和23年11月に宮崎県立吾田高等学校南郷分校として南郷小学校に設置された宮崎県立南郷園芸高等学校は、昭和25年4月に南郷町栄松へ移転し、昭和44年3月に再編整備により21年間の栄えある歴史に幕を閉じました。
このようにして、現在の日南農林高等学校は、昭和42年4月に県立日南農林第二高等学校として現在の地に新設され、昭和44年4月に校名を県立日南農林高等学校として新たな出発をし、44年間の歴史と伝統を築き上げてきましたが、今年度をもって閉校となります。本校の歴史は、明治30年から114年の長きにわたり営々と築かれ、卒業生総数10,783名を数えます。
現在、日本国内に約380校の農業に関する学科をもつ高等学校がありますが、その中でも農林高校の名称をもつ学校は僅かに26校だけであります。このいずれの学校も銘木を産する地域に設置された農業高校であり、本校の場合も例に違わず、広渡川、酒谷川流域に広がる日向弁甲として有名な飫肥杉を生産する地域の農業高校として親しまれてきました。
飫肥杉の歴史は古く、豊臣秀吉が天下統一した頃、当時の初代飫肥藩主であった伊東祐兵は朝鮮出兵の際、3万石の小藩主であったため小名の悲哀と肩身の狭さを身をもって体験しました。禄高をあげるため「どんげかせにゃいかん!」と考えた祐兵は、豊富にある山林の活用に目をつけ、伐採と同時に植林にも着手しました。これが飫肥林業の始まりであります。5代藩主祐実の頃に堀川運河の着工に取りかかり、五官五民制度で民衆の植林への熱を高めました。当時の山方奉行であった野中金衛門は飫肥杉の生みの親と呼ばれ、藩主祐鐘と共に現在の日南市の繁栄の基礎を築いたのであります。
旧日南農林高等学校、南郷園芸高等学校、現日南農林高等学校と変遷はありましたが、それぞれの学校のねらいは共通しています。それは、初代飫肥藩主伊東祐兵や山方奉行野中金衛門に続く、常に現状に満足せず、「どんげかせにゃいかん!」という課題解決のための強い意志と実行力のある人材を育てることにありました。
本校は、県立日南振徳高等学校に再編整備されますが、日南振徳高等学校は総合制専門高等学校として、あらゆる産業の基礎が学べる学校であります。産業構造が複雑化している現代に生きる若人には魅力に溢れた学校であります。飫肥藩の藩校であった振徳堂の名を引き継ぐ学校として、小倉処平や小村寿太郎に続く人材を育成されることを願ってやみません。是非、本校の良き伝統を受け継ぎ、新しい伝統を築いていかれるよう大いに期待しています。
さて、今回の閉校業務を遂行していく中で、県教育委員会・同窓会・PTAの方々には並々ならぬご支援とご協力を賜り、衷心より感謝申し上げます。我々教職員と、最後まで一緒になって頑張ってくれた96名の生徒達とこの1年間懸命に過ごしてきました。閉校という寂しさはありますが、創立114年の間に本校を巣立った10,783名の卒業生、学校運営に係わった748名の教職員のそれぞれが、日南農林高等学校がすばらしい学校であったと胸に刻み付けていることを信じて疑いません。
最後に、我が日南農林高等学校が本日ご臨席を賜った皆様方の脳裏に永遠に刻み込まれることを祈念いたしまして挨拶とします。
 旧日南農林高等学校
旧日南農林高等学校
 南郷園芸高等学校
南郷園芸高等学校
 現日南農林高等学校
現日南農林高等学校
