| 本校では,昨年度から校内研究における研究スタイルを変えました。全職員を2~3の研究班に分けるのが通常ですが, 本校では同じ課題を抱える教職員が6つの小グループを編成し,下のような研究内容について研究を進めてきました。各グループの研究内容については中間報告会や全体会等で全職員で共有し,本校の生徒に還元していきました。 今年度もこのようなスタイルで研究を進めていきます。昨年度は「学習指導」,「生徒指導」,「地域連携」で分類しましたが,今年度は「夢」,「力」,「心」となっています。各グループでの研究の成果を,随時,このホームページで紹介していきますのでご覧下さい。 |
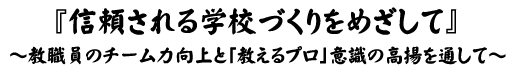 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校がかかえている課題や,より一層高めていきたい力をチーム別に研究していくことで,「教えるプロ」としての教職員の研究意識と指導力が向上し,このことを通して教育活動が充実し,「信頼される学校づくり」につながるであろう。 |
作 業 仮 説 |
||
夢 |
T-アクセス |
本校のホームページを作成・更新し,教育活動を発信することで,家庭や地域からの理解を得ることができるとともに,人材バンクを作成し,地域の教育力を活用することで,より効果的な教育活動ができるであろう。 |
T-夢ノート |
家庭学習を習慣化することによって,学力が向上するのではないか。 | |
力 |
T-学級力 |
生徒の学級に対する実態調査を行い,学級経営を通して,学級が抱えている課題を解決するための手だてをとれば,生徒が自分の居場所を感じ,集団としての力を発揮できる学級経営の充実につながるであろう。 |
T-自治力 |
日頃の学校生活を見つめさせ,話し合い活動や委員会活動,ボランティア活動に自主的に取り組ませることで,自ら課題に気づき,考え,実行する生徒が育ち,さらには集団の一員として,よりよい生活を築くために,自己を生かす能力をもった生徒を育てることができるであろう。 | |
心 |
T-ぶっくす |
以下の項目を実践していけば,本を読む生徒が増加し,落ち着いた学校生活を送れる生徒が育つであろう。 1 学校図書館の環境を整えること。 2 読書活動や図書館を利用した授業を取り入れること。 3 地域・家庭・公共図書館との連携を図ること。 |
T-すこやか |
心の力の育成と教師の連携を日常化していくことで,人間力をあらゆる場面で発揮できる生徒を育成できるであろう。 | |
T-道 |
学校行事を通して高められた人間性(団結力・自治力・思いやりの心など)をその後の学校生活においても発揮できるように,「道徳の時間」で補充・深化させていけば,より一層の道徳的実践ができ,人間性が高まるのではないだろうか。 | |
研 究 構 想 |
|
 |
| 各研究チームの研究については,下のチーム名をクリックして「flash paper」でご覧下さい。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
成果 |
Copyright 2007 Miyazaki Tomishima Junior High School. All Rights Reserved |