| 13年度の研究へ |
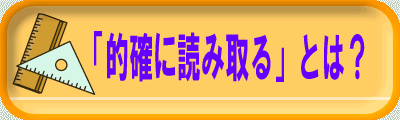
「題意を的確に読み取る」ということを,本校では次のように定義しました。
|
文章の内容を正確に理解し,題意に適切なイメージをもつこと  |
この思考ができることによって,児童は,問題解決への見通しがもて,解決への家庭を踏めると考えます。
例えば,このような問題が提示されたとします。
|
たかしくんは,あめを3こもっています。 おばあさんから5こもらいました。 あめはあわせていくつになったでしょう。 |
このような短い文章のよさは,問題の構造をとらえやすく,たし算など何を学ぶのかが示されているところだと考えます。
この文章問題を的確に読み取るためには・・・
具体的には,次のような思考ができるようになることだと考えました。
|
「文章問題を読んでみよう,解いてみよう」という意欲 教師は,児童が読むことへの抵抗感を少なくできるような工夫をする。 |
|
|
|
文章問題中で分かっていることの認識 文章問題中で,数量の分かっているものについて具体的で確実な数が認識できる。 |
|
|
文章問題中で尋ねられていることの認識 問いかけの文末や「いくつ」という不明数の表現から,このことが尋ねられているのだなぁと気付く。また,答えは,どんな単位なるのかも文章表現から読み取る。 |
|
立式を判断できる要素を見つける。 キーワードを活用したり,数の変化を具体的に絵図化したりして,例題だったら,「あわせる」というイメージがしっかりともてるようにする。 |
|
|
立式につなげるために・・・ | 児童が問題場面の具体的なイメージをもてるように,教師は,この認識がしっかりとできるような指導方法を工夫しなければならないでしょう。例えば,絵や図を描かせたり提示したり,動作化したり半具体物に置き換えてみたりするといった算数的活動をさせることも有効だと考えます。 |
| 13年度の研究へ |