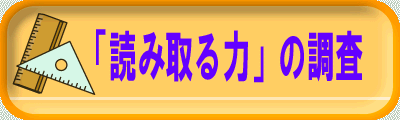|
「的確に読み取る力」を児童はどの程度もっているのでしょうか?
その実態を知るために,本校では「読み取りテスト」を作成し,その実施結果を分析することにしました。
具体的には,次のような問題を作成しました。
まず,次の文を読みましょう。そして,その文の内容から考えて,まちがいなくそうだといえることを,下の3つの文の中から見つけ出します。その答えを,解答欄に書いてください。
問題 けい子は,毎日図書館か家で読書をする。
ア けい子は今日も読書をする。
イ けい子は今日も図書館で読書をする。
ウ けい子は今日も家で読書をする。 |
また,文章問題を読んで,どれくらい演算決定できるかを調べるために,「演算決定テスト」を作成しました。それは,次のようなものです。
|
次の問題は,何算の問題か,解答欄に書きましょう。
「けんじさんは9さい,お父さんは45さいです。お父さんの年れいは,けんじさんの年れいの何倍ですか?」 |
他にも,文章問題についての意識調査,読書についての意識調査,計算力テスト,標準学力検査(国語,算数)を実施しました。また,日頃の文章問題の学習において気付いた児童の実態についても話し合いました。
それぞれの結果について分析したところ,主に次のような傾向が見られました。
|
☆ 算数の勉強は好きだが,文章問題を苦手と感じている児童がほとんどである。
☆ よく読まずに解答してしまったり,読むことを面倒だと感じてたりしている児童が少なからずいる。
☆ 例えば,上の例題のように,「何倍」というキーワードが入っていると,「かけ算」と答えてしまう傾向がある。つまり,よく読んで理解していないために,「逆思考」が苦手なことが伺える。
☆ 作問の機会を多く経験したり,いろいろな文章問題に自らかかわろうとしたりする児童は,考える楽しさや解けた満足感を味わっているようだ。
☆ 計算の力は確実に伸びてきているが,問題をよく読まないと解けない問題については,正答率が低くなっている。
☆ 国語のように長い文章となると,読まずに勘で答えたり,読んでも分からないためあきらめたりしてしまう。
☆ 語彙が豊富でない。言語事項に関する問題は間違いがとても多い。
☆ 読書が好きな児童は多い。しかし,絵だけを追ってしまったりしている児童もいる。 |
これを受けて,次のような研究をこれから推進していかなければならないと考えました。
 文章問題に興味をもって取り組めるような指導方法の工夫 文章問題に興味をもって取り組めるような指導方法の工夫 
 この問題では何を尋ねられているのか,それをしっかりと意識させる工夫 この問題では何を尋ねられているのか,それをしっかりと意識させる工夫
 文章に慣れ親しめるような工夫 文章に慣れ親しめるような工夫 |
|