| 16年度の研究へ | |
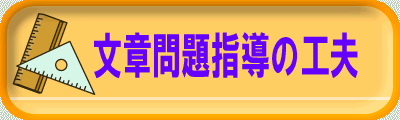
|
本校の児童の実態を受けて,文章問題に自信をもたせ,楽しく考え,主体的に解決していけるような体験を,授業の中でさせていくことが大切だと考えました。
算数の授業において,題意を的確に読み取る力を育てるためには,まず次の2つがポイントになると考えます。
この2つに焦点を当てて,これからその具体的な方法について次のように考えてみました。 |
| 16年度の研究へ | |
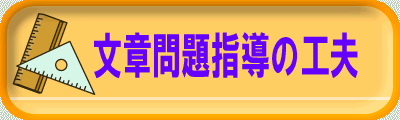
|
本校の児童の実態を受けて,文章問題に自信をもたせ,楽しく考え,主体的に解決していけるような体験を,授業の中でさせていくことが大切だと考えました。
算数の授業において,題意を的確に読み取る力を育てるためには,まず次の2つがポイントになると考えます。
この2つに焦点を当てて,これからその具体的な方法について次のように考えてみました。 |
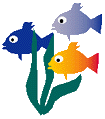 文章問題に的着くまでの過程(学習活動)を大切にする。
文章問題に的着くまでの過程(学習活動)を大切にする。|
文章問題につながるような,学習活動を取り入れてみよう。つまり,五感を使って,問題場面を体と心(頭)で理解させるという方法です。
主に,低学年で重視していこうと考えました。 例えば,次のような活動が考えられます。
この他にも,本校の第1学年では,次のような取組がなされています。
|
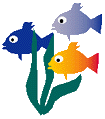 文章問題を,構造化してとらえられるようにする。
文章問題を,構造化してとらえられるようにする。|
文章の中で,分かっていることは何なのか,尋ねられていることはどういうことなのかを,しっかりと理解できるようにするということです。 発達段階によっても,その方法は違ってくると考えます。 例えば,次のような活動が考えられます。
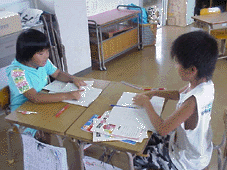 ペア学習で自分自身の読み取りについて話し合うことにより,友達と読み取りを確認し合い,的確な読み取りへと到達することができると考えます。 その結果,正しい読み取りのもとで解決が進められることになるでしょう。 また,読み取りを苦手とする児童にとっては,友達の読み取りの方法を知ることによって,どうすれば正確に読み取れるのか,読み取ったことをどう表現すればよいのかを理解していくようになるのではないかと考えました。 さらに,授業で適用題に取り組ませる時間を設定することにもしました。 適用題に取り組むことによって,その時間に学習したことを,再度ふり返りながら確認することができます。また,確実に自分の力で解けたという自信をもたせることも可能です。 さらに,学習したことを生かしながら読み取りのポイントを押さえられると,正確な解答に結びつくことから,読み取りへの自信に結びつくことも考えられます。 |
| 13年度の研究へ |