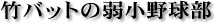 |
|
宮崎南高校の野球部は南高校創立の翌年に創設された。しかし、中学時代の経験者は数えるほどだった。勉強との両立で練習時間も少なく、高校球界では弱小高校の1校にしか過ぎなかった。
昭和50年前後には部員数の減少から廃部の危機に追い込まれたこともある。
予算も少なく、金属バットも高くて買うことができなかった。竹を接着剤で固めた竹バットを使っていたという。
バッティングでボールの当たり所が悪いと、ものすごいしびれが部員たちの腕と手を襲った。 |
 |
|
|
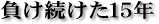 |
|
右の表は野球部創設から昭和52年までの夏の大会の成績である。昭和51年にベスト8に入ったことを除くと、部創設の昭和38年から15年間、2回戦突破は1回だけであった。
コールド負けが部員たちを落ち込ませた。練習試合も満足にできなかった。
ただ「野球を続けたい」という部員たちの熱意だけが、南高野球部をかろうじて支えている時期でもあった。
|
| 年度 |
成績 |
| 昭和38年 |
2回戦敗退 |
| 昭和39年 |
2回戦敗退 |
| 昭和40年 |
1回戦敗退 |
| 昭和41年 |
1回戦敗退 |
| 昭和42年 |
緒戦2回戦敗退 |
| 昭和43年 |
緒戦2回戦敗退 |
| 昭和44年 |
1回戦敗退 |
| 昭和45年 |
3回戦敗退 |
| 昭和46年 |
2回戦敗退 |
| 昭和47年 |
1回戦敗退 |
| 昭和48年 |
1回戦敗退 |
| 昭和49年 |
2回戦敗退 |
| 昭和50年 |
1回戦敗退 |
| 昭和51年 |
初ベスト8 |
| 昭和52年 |
緒戦2回戦敗退 |
|
|
|
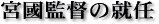 |
|
昭和53年、宮國則成(みやくにのりしげ)先生が監督に就任した。国語の教師として南高校に赴任してきて5年目のことだった。
このとき、部員は6、7人しかいなかったという。野球が満足にできる状態ではなかった。
宮國監督は、まず父母の会をつくった。部員の保護者にまず応援してもらおうと思ってのことだった。こうしてピッチングマシンを手に入れる。これは当時の南高校野球部にとっての秘密兵器であった。
それまでバッティング練習をしたくても、投げる生徒もいない、いてもストライクの投げられないチームだった。マシンのおかげで練習時間を有効に使え、部員はバッティングの力をつけていったのである。
グランドに出たら真剣勝負。短い時間を有効に使った厳しい練習が始まった。雨の日は柔道場で、ラケットで打った硬式テニスボールをグラブで飛んでとるというような練習もした。カッパを着てグランドに出てキャッチボールもやった。
炎天下、あまりののどの渇きに、グランドのわだちに溜(た)まった水を飲んでいた外野手もいた。
|
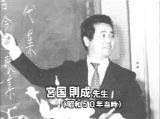

 |
|
|
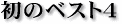 |
|
こうした効率的な厳しい練習の成果は次第に現れ始め、数年後には県大会の上位に名前を連ねるようになってきたのである。
昭和62年の夏には、好投手磯貝を擁してはじめてベスト4進出。その年の秋の九州高校野球大会にも県の代表として初出場し、甲子園まで今一歩のところに立ったのであった。
宮國監督が就任して9年目のことである。
そして翌年の昭和63年、春の九州大会で強豪相手にベスト4に入り、自信を得た南高は甲子園に照準を合わせ、再び猛練習を開始したのだった。
|

 |
|
|
 |
|
7月10日、第70回全国高校野球宮崎大会の幕が切って落とされた。
シード校が次々に姿を消す波乱含みの中で、南高は2年連続のベスト4から、準決勝へと駒を進めた。対戦相手は都城工業高校。これに勝てば決勝である。
試合は、9回まで手に汗握る接戦となる。
1番レフトの1年生木村拓也の活躍で、一度は3対1と引き離したものの追いつかれ、5対5のまま9回を迎えたのである。南高校の攻撃だった。
ここで1番サードの中原章典が、思い切りのいいバッティングで3ベースヒット。そのあとヒットが続き満塁となった。さよならのチャンスである。スタンドの南高の生徒たちも職員も、あらん限りの声援をおくる。そして、6番ファースト南村圭亮を迎えた。
南村の打球はセンターの頭上を大きく超えるさよならヒット。このとき、南高校は初の決勝出場が決まったのである。 |

 |
|
|
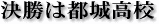 |
|
主将だった4番キャッチャー深江義和は、決勝の相手が都城と決まったときに「勝ったな」と思ったそうである。
それほど南高校のナインは波に乗っていた。
そして決勝は、8対1と都城を下し甲子園出場を決めたのだった。
|


 |
|
|
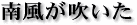 |
|
甲子園の開会式。宮崎南高校の入場行進を部員たちの親、そして宮國監督たちがアルプススタンドで見守った。
さらにテレビを通じて、南高校を出た全国の鵬(おおとり)達が、万感胸迫る思いでこの行進を見つめていた。 |

|
甲子園の1回戦の相手は、青森代表弘前工業であった。最初にバッターボックスに立った中原はここでも思い切りのいいバッティングを見せる。いきなりの二塁打。
甲子園には南風が吹いていた。続く依網の送りバントがヒットになり、3番川口がスクイズを決めてまず1点。続く4番深江がヒットでつないで、1回で2点を上げ、試合の主導権を握ったのだった。 |

|
8対4で弘前工業に勝った南高は、甲子園で初めての校歌を聞くことになる。このときはまだ、甲子園で1勝をあげなければ、校歌を甲子園で歌うことはできなかったのである。
宮國監督は「これで面目を保てた」とほっとしたという。 |

|
そして、宮崎から駆けつけた大応援団と野球部員たちの歌う校歌が、球場に全国に響き渡った。
マネージャーの山下智穂は、全国にこの校歌が流れているのだと思い流れる涙を拭いながら、歌った。 |

|
二回戦は連続出場の強豪沖縄水産と対戦した。
5対1で敗れはしたが、実にさわやかな南風を甲子園に届けて、南高校は去っていったのだった。 |
 |
|
|
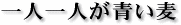 |
|
今、甲子園に出場した野球部員たちは、医者や学校の先生、技術者そして銀行や企業の中核となって、社会に貢献する鵬(おおとり)達となった。
当時1年生だった木村拓也はプロ野球に入り、広島カープの主軸として人々に夢を与えつづけている。
南高校の正門を入って20mほど歩いた左手の木陰に、石碑が立っている。1988年の甲子園出場を記念して建立されたものだ。そこには校歌の一節をとった次の言葉がかかれている。
ぼくら
ひとりひとりは
強い一本の
青い麦だった
強い一本一本の青い麦たちは、その実りを大切に収穫し、新しい世界に羽ばたいていった。
野球部室の壁には、負けつづけた先輩達の文字が残されている。
「野球は結果じゃない」
甲子園に出場した鵬達をその何百倍何千倍の鵬達が今も誇りにしている。
ありがとう。宮國監督と部員達。
ありがとう。南高。
|

 |
|
|