|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
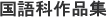 |
平成17年度 第44号から |
|
|
|
|
 |
|
|
|
初めて乙武さんを見た時、その姿に正直驚いた。と同時に失礼かもしれないが、かわいそうとも感じてしまった。しかし、彼の表情はとても限るく、堂々としていて、そんな障害をかかえている人には見えなかった。この人は、一体どんな人生を歩んできたのだろうか。
重度の障害を持ちながら、それを全く感じさせない彼の性格は、もって生まれたものであるかもしれないが、それ以上に、周囲の人の彼への接し方によるものが大きいと思う。
小学校一年から四年まで担任であった高木先生。この先生と出会わなかったら今の乙武さんはなかったと思う。
手足の無い彼に変わり何でもしてあげようと思う気持ちは誰もが持つもので悪い事ではないが、先生はあえて自分でできる事は自分でさせようとした。確かにまわりの人間が何でも手助けしていたら、「待っていれば、誰かがしてくれる。」という甘えた気持ちが育ってしまうにちがいない。
また先生は、今まで乗っていた電動車いすも校内で許可なく使用することを禁じた。それは、車いすに乗っていることでの優越感をなくし、「障害者=特別視Jという図式をくずすためであった。もう一つは、成長期である小学生の時期に車いすばかりたよっていると筋も鍛えられないと考えたからだ。
当然、反対意見も出されたが、先生は自分の考えを曲げなかった。「今だけかわいがっでやることはいくらでもできる。たが、この子はいつかひとりで生きてかなければならない。その将来を考え、今何をしてやることが本当に必要なのかを考えていくのが、私の役目なのだ」との信念からだ。この先生の決断はまちがいではなかったと思う。ずっと車いすに乗り続けていたら、車いすなしでは生活できない障害者となっていただろうし、生活の幅ももっと違ってきただろう。真のきびしさは、真のやさしさであることを教えられた。
中学に入ってからの彼には、ますます驚かされる。バスケ部に入部するのだ。しかも、試合にまで出ている。それは、彼のがんばりがあったからではあるが、何よりも、チームメイトの支えや思いやりがあったからだと思う。
高校でもアメフト部に入部する。しかし、さすがに試合に出るわけにはいかない。そこで、彼が監督からまかされたのが対戦相手のデータ集めであった。障害のある者が、スポーツのクラブに入部することなど、全く考えられない。普通の健常者と同じように出来るはずがないと私たちは頭から思い込んでしまっている。しかし、この本を読んでいると、まわりの人の理解や思いやりでできるものなのだと改めて考えさせられた。
彼がこのような性格に育ったのには、やはり、両親によるものが一番大きいだろう。普通、我が子が障書を持って生まれてきたら嘆き悲しみ、あまり人目にふれないようにしてしまう親の方が多いかもしれない。彼の両親は手足のない我が子を初めてみた時、「驚き」でもなく、「悲しみ」でもなく、「喜び」だった。このことは、非常に大きな意味を持っていると思う。親が我が子を「かわいい」という気持ちよりも、「かわいそう」という気持ちの方が強ければ、子どもも、そのことを敏感に感じとり、「自分は、やっぱりかわいそうな人間なんだ。」と後ろ向きの人生を歩んでしまうだろう。
今まで障害者に対して偏見があったが、この本を読んで、乙武さんのことを知ると、何ら普通の健常者と変わらないと思えてきた。背の高い人、低い人。色の黒い人、白い人。それと同じように、手足の不自由な人もいてなんの不思議もない。単なる身体的特徴にすぎないと思えてきた。
しかし、今の日本では、障害をもった人が一人で街の中を自由に動き回るのは困難である。多くの人の手助けが必要である。自分一人ではできないことが多いために、「かわいそう」に見えてしまうのである。
環境さえ整えば、体の不自由な障害者でも障害者でなくなる。だれもが自由に行動できるような社会が早くくることを願いたい。
|
|
 |
|
|